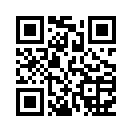2016年12月16日
左官顧問直伝~漆喰壁塗りのコツByドラえもん~
狭い所は好きな方である
が!しかし・・・
直角三角形にむりくり肩幅とつまさきをおさめて塗る漆喰壁

プロの左官屋さんはこんな所はどうやって塗るんだろうね
一番隅っこの鋭角なんか寝ながら塗りましたがね、えぇえぇ・・・
さて壁塗りの始めは作業環境を整えることから
床に養生シートなどを敷くのはもちろん
高い所の足がかりに脚立などを置く場合は畳をダメにしないようコンパネなどの板を敷いた方がよろしい
板の上の方が安定したる足場を確保せしめることもタイヘンよろしい
漆喰壁は散り際と呼ばれる壁と柱の接するキワッキワの始末がキレイに出来ていると美しい
散り際にマスカーテープ(シート付き)を貼って

※画像はモノタロウより拝借
汚したくない所をシートでカバーしたり

マスキングテープなどで

※画像はモノタロウより拝借
柱と壁の散り際をマスキングしておく

こんな↑カネの出ていない製材でもマスキングしておくと散り際の微妙な曲面も塗りやすい
漆喰を塗り終わってからマスキングテープを剥がせば
あ~らキレイ!
美しい散り際が現れるのである
余分にはみ出たり柱についた漆喰を濡れぞうきんで早々に拭きとるのだけれどこのひと手間をしておくだけで速やかにせしめる
これは便利!
※ちなみにモノタロウは御用達であるがからいくらかの斡旋料をもらったりしているわけではない
上客として認めて頂いたのか先日かなり本気な人向けカタログが届いた
換気扇(写真左上に)もマスキングテープとスーパーのレジ袋で覆った

(写真は既に漆喰塗っている段階で一部白く乾いているのは最も塗りにくい三角地帯から始めたからだす)
マスキングシートの幅が1100mmもあって始末にワルかったから
コンセントもコードもマスキングせしめん
素人はそれらが邪魔するため鏝(コテ)さばきがますますうまくいかずストレスになるのであるからしてあらかじめ汚してもいいようにしておくのは賢明である
左様に作業環境を整えれば次に塗りに入る
予め1cm以上散りが切れている所には砂多めの漆喰「砂1:漆喰1」で隙間を埋めておく
(それゆけ左官顧問の渡辺氏直伝!)
さらに下地材(ここでは主に石膏ボード)にカチオン系のシーラーを下塗りした
ケミカルなものを嫌う場合は「こんにゃく粉」を溶いて下塗りに使うらしい
漆喰は下地によっては水分を吸われてとても塗りにくくなる
シーラーを塗っておくと「食いつきがよい(左官顧問渡辺氏弁)」と言う
密着しやすいということである
既存の壁に漆喰を塗る時などに浮き出てしまう汚れやシミや木材のアクなどが出ないようコートする目的もある
シーラーが乾いたら(すぐ乾く)漆喰を塗っていく
基本的には塗る面の「下から」及び「左角(右ききの方)」から塗っていくのがよい
写真でグレーに見える壁は塗りたての色(その下部分はプロがそしてその上部分はわたすが塗ったとこ)

乾くとこれが上の面のように白くなるので色の出方は乾いてから見てみないとわからぬ
色の見え方は光の加減でも変わる
この漆喰は石灰・白砂・土・麻スサで手作りしたるものだが乾いてからも暗い部屋ではグレーがかって見え太陽の射す所では真っ白に見える
土の色の特徴らしい
乾いてみないとワカラない所もオモシロイ
その土地によって緑や青色の出る土もあるらしい
漆喰は二度から三度は重ね塗りする
今回は二度塗り
1回目の塗りのコツはコテを押しつけるようにして砂粒ほどの厚さ(!)に塗る!
と弟子が何かと相談するにつけ左官渡辺師匠が口を酸っぱくしておっしゃる
始めの塗りが乾き始めて完全に乾かない前に(微妙な塩梅である)二度目を塗る
あまり二度目の塗りが早すぎれば一度目に塗った漆喰が動いてしまう
かと言って完全に乾いてからだとやはりすぐに水分を吸われて薄く均一に塗るのがむつかしくなるのである
その季節やその日のお天気にもよって水の引き具合や乾き方はずいぶん違う
前に誰かが「左官だけはネットでも情報が少ない」と言っていたがこれだけは体験して身につく感覚の技術ではなかろうかしら
おおよそ部屋の三面は塗り終えて

次は押入れの中の壁・・・
天井もあらわしにしたことだし天袋(押入れの上)をロフトにしようという考え!
なのだがあるもので賄う「お金をかけずに(出来るだけね)みんなの家をみんなでつくろうプロジェクト」である
石膏ボードも在庫が無くなったのでもともとそこに張ってあった数mmのボロベニヤを再利用~
したらシーラーを塗ったところ水を含みべろべろぼこぼこに素晴らしく波打ったわけ

それならとシーラーを5回くらい乾いては塗りを繰り返して固めてやった
さらに余っていたかつての床材を張ってみた

う~んうまくごまかしたものである
しっかり固まって機能的にも問題ないようである(今のところな)
押入れ下の段ではそのべろべろぼこぼこがひど過ぎて穴が開きそうだったのでたっぷり厚めにデコデコに砂漆喰で固めてやった
ダメでもともとと想ってたら存外しっかり固まってしまったのである
う~んしめしめである
電気の配線もこんなのにおさめて

(塩ビパイプを割って配線をおさめようかと想ってる話をしたら新井由己さんが薦めてくれたし184円で送料無料だったし買ったもん♪)
キレイにスッキリ

漆喰塗りも完了したので床養生もはずして畳がひさしぶりにこんにちは

畳から板張りに変えようかとも想っていたがやっぱり畳がいい
押入れをデスクとかにしてふすまもはずしておこうかと想ったりもしたのだが・・・
ふすまを入れてみたらやっぱりなんか安心するので旧来どおりにふすまを戻すことにした

するって~と・・・
あれですか・・・
あすこで寝るってあんた・・・・!!!
ドラえもんっ!

子供の頃に押入れをMy個室にしたかったのは絶対わたすだけではないとおもふのである・・・
が!しかし・・・
直角三角形にむりくり肩幅とつまさきをおさめて塗る漆喰壁

プロの左官屋さんはこんな所はどうやって塗るんだろうね
一番隅っこの鋭角なんか寝ながら塗りましたがね、えぇえぇ・・・
さて壁塗りの始めは作業環境を整えることから
床に養生シートなどを敷くのはもちろん
高い所の足がかりに脚立などを置く場合は畳をダメにしないようコンパネなどの板を敷いた方がよろしい
板の上の方が安定したる足場を確保せしめることもタイヘンよろしい
漆喰壁は散り際と呼ばれる壁と柱の接するキワッキワの始末がキレイに出来ていると美しい
散り際にマスカーテープ(シート付き)を貼って

※画像はモノタロウより拝借
汚したくない所をシートでカバーしたり

マスキングテープなどで

※画像はモノタロウより拝借
柱と壁の散り際をマスキングしておく

こんな↑カネの出ていない製材でもマスキングしておくと散り際の微妙な曲面も塗りやすい
漆喰を塗り終わってからマスキングテープを剥がせば
あ~らキレイ!
美しい散り際が現れるのである
余分にはみ出たり柱についた漆喰を濡れぞうきんで早々に拭きとるのだけれどこのひと手間をしておくだけで速やかにせしめる
これは便利!
※ちなみにモノタロウは御用達であるがからいくらかの斡旋料をもらったりしているわけではない
上客として認めて頂いたのか先日かなり本気な人向けカタログが届いた
換気扇(写真左上に)もマスキングテープとスーパーのレジ袋で覆った

(写真は既に漆喰塗っている段階で一部白く乾いているのは最も塗りにくい三角地帯から始めたからだす)
マスキングシートの幅が1100mmもあって始末にワルかったから
コンセントもコードもマスキングせしめん
素人はそれらが邪魔するため鏝(コテ)さばきがますますうまくいかずストレスになるのであるからしてあらかじめ汚してもいいようにしておくのは賢明である
左様に作業環境を整えれば次に塗りに入る
予め1cm以上散りが切れている所には砂多めの漆喰「砂1:漆喰1」で隙間を埋めておく
(それゆけ左官顧問の渡辺氏直伝!)
さらに下地材(ここでは主に石膏ボード)にカチオン系のシーラーを下塗りした
ケミカルなものを嫌う場合は「こんにゃく粉」を溶いて下塗りに使うらしい
漆喰は下地によっては水分を吸われてとても塗りにくくなる
シーラーを塗っておくと「食いつきがよい(左官顧問渡辺氏弁)」と言う
密着しやすいということである
既存の壁に漆喰を塗る時などに浮き出てしまう汚れやシミや木材のアクなどが出ないようコートする目的もある
シーラーが乾いたら(すぐ乾く)漆喰を塗っていく
基本的には塗る面の「下から」及び「左角(右ききの方)」から塗っていくのがよい
写真でグレーに見える壁は塗りたての色(その下部分はプロがそしてその上部分はわたすが塗ったとこ)

乾くとこれが上の面のように白くなるので色の出方は乾いてから見てみないとわからぬ
色の見え方は光の加減でも変わる
この漆喰は石灰・白砂・土・麻スサで手作りしたるものだが乾いてからも暗い部屋ではグレーがかって見え太陽の射す所では真っ白に見える
土の色の特徴らしい
乾いてみないとワカラない所もオモシロイ
その土地によって緑や青色の出る土もあるらしい
漆喰は二度から三度は重ね塗りする
今回は二度塗り
1回目の塗りのコツはコテを押しつけるようにして砂粒ほどの厚さ(!)に塗る!
と弟子が何かと相談するにつけ左官渡辺師匠が口を酸っぱくしておっしゃる
始めの塗りが乾き始めて完全に乾かない前に(微妙な塩梅である)二度目を塗る
あまり二度目の塗りが早すぎれば一度目に塗った漆喰が動いてしまう
かと言って完全に乾いてからだとやはりすぐに水分を吸われて薄く均一に塗るのがむつかしくなるのである
その季節やその日のお天気にもよって水の引き具合や乾き方はずいぶん違う
前に誰かが「左官だけはネットでも情報が少ない」と言っていたがこれだけは体験して身につく感覚の技術ではなかろうかしら
おおよそ部屋の三面は塗り終えて

次は押入れの中の壁・・・
天井もあらわしにしたことだし天袋(押入れの上)をロフトにしようという考え!
なのだがあるもので賄う「お金をかけずに(出来るだけね)みんなの家をみんなでつくろうプロジェクト」である
石膏ボードも在庫が無くなったのでもともとそこに張ってあった数mmのボロベニヤを再利用~
したらシーラーを塗ったところ水を含みべろべろぼこぼこに素晴らしく波打ったわけ

それならとシーラーを5回くらい乾いては塗りを繰り返して固めてやった
さらに余っていたかつての床材を張ってみた

う~んうまくごまかしたものである
しっかり固まって機能的にも問題ないようである(今のところな)
押入れ下の段ではそのべろべろぼこぼこがひど過ぎて穴が開きそうだったのでたっぷり厚めにデコデコに砂漆喰で固めてやった
ダメでもともとと想ってたら存外しっかり固まってしまったのである
う~んしめしめである
電気の配線もこんなのにおさめて

(塩ビパイプを割って配線をおさめようかと想ってる話をしたら新井由己さんが薦めてくれたし184円で送料無料だったし買ったもん♪)
キレイにスッキリ

漆喰塗りも完了したので床養生もはずして畳がひさしぶりにこんにちは

畳から板張りに変えようかとも想っていたがやっぱり畳がいい
押入れをデスクとかにしてふすまもはずしておこうかと想ったりもしたのだが・・・
ふすまを入れてみたらやっぱりなんか安心するので旧来どおりにふすまを戻すことにした

するって~と・・・
あれですか・・・
あすこで寝るってあんた・・・・!!!
ドラえもんっ!

子供の頃に押入れをMy個室にしたかったのは絶対わたすだけではないとおもふのである・・・
Posted by 純chan at 22:00
│今週のプロジェクト報告