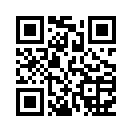2016年09月07日
写真で見るエコ化DIY~床断熱の1~
1日目の午後
「電動丸ノコの使い方」
電動丸ノコってのはこれ↓

いろんなメーカーのものがあるんだよ
始めはこんなワークショップで大工さん達が使っているものをいくつか借りて試してみたり慣れてからMy丸ノコを買うのがいいね!
丸ノコに限らず電動工具は使い慣れてくるとパワーのあるものが使いやすく感じるようになったりもするからね
慣れてから見立てた方がいいと思うよ

こんな冊子がホームセンターにはたくさん置いてある

これはジャンボエンチョーの「DIYハンドブック~電動ノコの使い方」です
読めばやってみたくなるというもの
読めば欲しくなるというもの・・・
うまく出来ていますな
さぁ匠部あきと君のお手本を見たら早速やってみるよ

そこいらにあった廃材の角材を切ってみまそ
丸ノコガイドっていうのを使ってるからまっすぐ直角に切れるん筈だよ
(ガイドをちゃんと使えてればね)
やえちゃん緊張して近過ぎかな・・・
腹切るよ・・・

前田社長
向こうから覗いて一生懸命なやえちゃんが・・

畑楠はたっくすさん
首のタオルが巻き込まれたらコワい(保護カバーがあるから大丈夫だろうけどね)

見守るあきと君がいつもこぶしを握っているのは殴りたいわけではない
教える人も見守りながら力が入るのだ
気がつくと手を握っているんですな
私もいつもそうです
何でもきれ~に切っちゃう道具なんですからね
しかも回ってんですから何かが巻き込まれたら非常にコワいです
こうして写真で客観的に人と自分のフォームを見てみるのも善い学びになるんじゃないかしらね
みなさん初めての丸ノコでした
妙な汗かきましたね
さぁそしたら床断熱施工のはじまりはじまり~
まず畳を起こしますぜ

畳の裏に書いてある「八南西」という表記は「八畳の南西」
その畳は八畳の間のどこかという位置を表していて後で戻す時にどこにあったものか判断をいたすわけであります
長く使っているとよく踏まれるところとか少々変形して5mmも違えば隙間が空いたりハマらなくなったりするから定位置におさめるんでしょうかね
それから畳の裏に古雑誌をまとめる時に縛るようなヒモが結んであるんだね
これを持って運ぶの
これがあるだけでスゴい楽よ~
あっ
なんだこの穴はっ!

怪獣が踏み抜いた跡ではないかっ!
隊長っ!この足形はゴジラのものと想はれますっ!

ゴジラめっ!函南にも表れたのかっ!
しかしこのゴジラ外反母趾ひどくないか・・・?!

う~ん・・・ウルトラ警備隊は昭和の家に似合いすぎる・・・
(という連想に走るのが昭和人の証・・・)
畳の下には下地板が敷いてあるんだね
厚さは12mmだよ
ゴジラが踏み抜いた下地板は他のラワンベニヤと違う集成材っていうのかしら
すぐに劣化して床みたいな荷重には耐えられそうにない材質なんだものねぇ

ややっ!
笹竹がっ!
生えてきたけど2~3mで枯れておるな

下地板の下には「根太」とそれを下で交差して支える「大引き」という構造
ここで根太は45mm×40mmの角材
大引きは100mm×100mmとか
もとは105mmだったんでしょうけど長い年月で乾燥して木も痩せるんだね
「とか」って言うのは四隅が直角に製材された角材でなかったりしているのであります
樹皮がついたままだったり一辺は丸かったり・・・
昭和の家ではそんな材がいたるところで使われてますよ
だから何かとちょっとタイヘン(なことは何か・・・また後で出てくるよ)
下地板は根太にコースレッド(ビスまたはネジのことね)でうちつけられているんだよ
錆びてもろくなってるからインパクトドライバーがネジ頭の溝をつぶしがち
すべってネジが回らなくなるから抜けまへん・・・
するってぇとバールが登場です

根太と板の間に打ち込んでぐいっとな・・・
それぐいっとな
下地板を剥がした状態
根太の上に立っているのもけっこうバランスとるのタイヘン

これをまたいで行き来するのは大腿二頭筋にきくことを翌日か年齢によっては翌々日に思い知るのである

ここであらわになった地面のお掃除
大事~
木くずやホコリがあるとダニやアリや虫たちの格好の食糧とか住処になりやすいんだって!
甲斐の匠オニギリさんが言ってたよ
そうそう!押入れの床下断熱もやらずばなるまいっ

押入れの床板は畳の下地よりずっと薄く5.5mmだよ
押入れの床がべこべこしたりして頼りなく感じる経験あるあるでしょう
この薄さで断熱材も気密シートも入れなけりぁ押入れが湿っぽくなるのも壁板が湿気や結露でいや~な感じに変色するのも当たり前ずらね(いきなりのby函南語)

床を裸にしてやったらそ~ら気流止めだっ

床下の高湿度で低温な空気が室内へ入って来ないようにするだよ
(またしてもby函南語)
断熱施工をしたって隙間があっちゃダメだら?(ダメでしょ?)
隙間って狭きゃぁ狭いほどひゅ~と吹き抜けるんだからね
ってんで厳しい目つきと偉そうな態度で監督中

最近じゃ気流止め専用の真空パックみたいなグラスウールもあるだってさ
所定の場所に置いてからプチっとすれば空気が入って膨らむっていう便利なヤツ
ここで使ってる普通のやつより少々お高いわよ
ここでは天井断熱で使ったのと同じグラスウール「アクリアネクスト」470mm幅のを300~400mmの長さで切って加工して使うのだ
切って

貼って

それを防水面を外側にしてふたつおりにして詰めるだよ
(「こちらを室内側に・・・」とか商品に印刷してあるだから素人さんにもすぐわかるさ)
つねさんふたつ折り中・・・

よくおワカリの大澤親分はサクサク詰めていくら?(詰めていくでしょ?)

よくおワカリでない私はひとつひとつ考え込む
ふたつ折にした輪の方(開いてない山折りの方)を上にしたものか下にしたものか・・・
う~ん・・・
床下から壁の面の隙間を空気が上がって来ないようになんだからぁ・・・
防水面外側で~・・・
輪の方をぉ~・・・
ん~~~~っと下向きだっ!え?上だっけ?

と!お年寄りが外出前に鍵かけ火消し確認を繰り返すように毎回つぶやきつつ確かめながらという正確さを期すのであった
(少しおつむが緩んでくる年頃という説もある)
気流止めを入れたらこんな感じ~
基礎(コンクリート)の上に乗ってる土台の木材の上に詰め詰めだっ!

ややっ!黒子が床下に寝ているぞっ!

ではない・・・
高さ230mm!つまり23cmを通れるくらいスマートなんだぞ!とご披露しているわけでもない
いざ!押入れ下の気流止めに出陣するところでありますっ!
そ~らこうだっ!

この時点では断熱材も押入れの床板を取らずにもぐって下から入れようという計画だったからね
実際やろうとしたら根太がけがあるので下からは入れられなくて作戦変更
押入れの床板をはいで上から入れたんで・・・はい
さぁこれでついに断熱材スタイロエースを入れられるとこまで来たじゃ!(来たね!)
ぢゃ!いきなりだけど続きはまた明日ね!
8月から土曜のみ参加の「1日コース」も誕生!
詳細とお申し込みはこくちーずproからどうぞ
http://www.kokuchpro.com/event/ietukuri/66046/
Posted by 純chan at 23:46
│それゆけエコ化DIY!